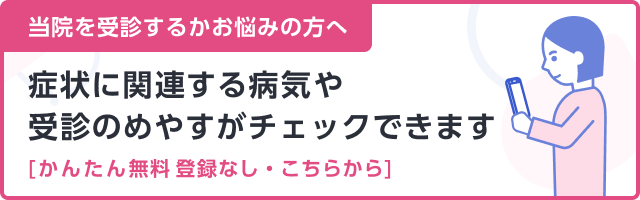パーキンソン病に新たな光:iPS細胞治療の臨床試験結果が明らかに
パーキンソン病に対する新しい治療法として、幹細胞を使った研究が注目を集めています。2025年4月には、iPS細胞などを使った最新の臨床試験結果が2件、世界的な科学誌「Nature」に同時に発表され、大きな話題となりました。
【幹細胞治療の進歩と期待】
幹細胞は、体のさまざまな細胞に変化できる特殊な細胞です。無限に増える能力があり、将来の医療を変えると期待されています。特にパーキンソン病では、運動をつかさどる神経が減ってしまうため、幹細胞から神経細胞を作って補う試みが進んでいます。
この分野では1980年代から研究が始まりましたが、当時は胎児の脳細胞を使っていました。しかし、倫理的な課題や供給の難しさがありました。そこで、iPS細胞(人工多能性幹細胞)やhES細胞(ヒト胚性幹細胞)といった幹細胞が注目されるようになったのです。
【iPS細胞治療の臨床試験:京大の取り組み】
京都大学では、iPS細胞から作ったドパミン神経のもとになる細胞を、7人のパーキンソン病患者の脳に移植する臨床試験を行いました。これは「第I/II相試験」と呼ばれ、安全性と有効性の両方を確認する段階の試験です。
移植から2年間の経過観察では、重篤な副作用は見られず、4人の患者で症状が改善する傾向が見られました。中でも、薬を使っていないときの運動能力(OFFスコア)や、薬を使っているとき(ONスコア)の評価が改善したことが注目されます。
さらに、PETという画像検査では、脳内でドパミンを作る能力が増えていることも確認されました。これは、移植した細胞が実際に働いている証拠とも言えます。
【海外でのhES細胞治療:BlueRock社の挑戦】
一方、米国とカナダでは、BlueRock Therapeutics社がhES細胞を使った神経細胞の移植試験を実施しました。こちらも12人の患者に対して行われ、移植後18〜24ヶ月の経過を観察しました。
結果としては、移植に伴う大きな副作用はなく、特に高用量の治療を受けた患者では、運動症状の改善が見られました。MDS-UPDRSという国際的な評価尺度で、平均して23点近くスコアが改善しています。
また、こちらでもPET検査でドパミンの増加が確認されました。免疫抑制剤の使用を終了した後も、移植細胞が生き残っていると考えられています。これにより、細胞移植が長期間にわたって効果を発揮する可能性が見えてきました。
【今後の展望と実用化への課題】
今回の2つの臨床試験はいずれも規模は小さいものの、安全性と効果の可能性を示す重要なステップとなりました。現在、より多くの患者を対象にした大規模な第III相試験の準備も進められています。
細胞治療は、薬やリハビリと組み合わせることで、より高い効果を期待できます。また、患者本人の細胞からiPS細胞を作り、拒絶反応のリスクを減らす「自家移植」も今後の有望な選択肢と考えられています。
パーキンソン病は、現在も完治が難しい病気ですが、こうした細胞治療の進展によって、将来的に新たな治療の道が開けるかもしれません。治療法の選択肢が増えることは、患者やその家族にとって大きな希望です。
※この記事は、2025年4月時点でNature誌に掲載された最新の医学論文と、京都大学・BlueRock社からの公式発表をもとに作成しました。