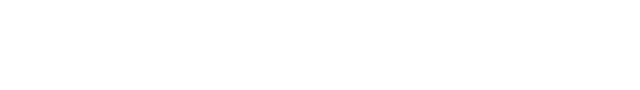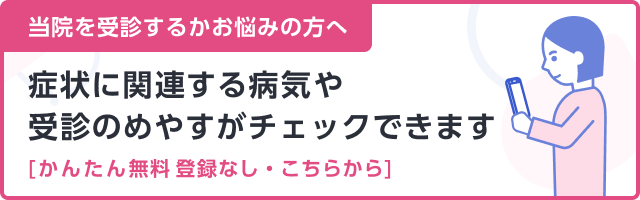パーキンソン病の新しい治療の可能性について
パーキンソン病は体が動かしにくくなる病気の一つで、特徴的な症状は体の動きが緩徐になる無動、手や足が震える振戦、体が固くなる固縮、バランスが取りにくくなる姿勢反射障害で、これらを総称して4大症状と呼びます。
原因として、黒質などの脳内の神経細胞が減少することにより、神経伝達物質の1つであるドパミンが減ることが考えられています。
パーキンソン病の治療の中心は薬による治療とリハビリテーションに加え、外科的治療である脳深部刺激療法とデュオドーパがあります。
しかしこれらの治療はパーキンソン病の根本的な治療ではなく、症状を緩和させることが中心の治療です。
これに対し根本的な治療として期待されているのが、iPS細胞を用いた治療と遺伝子治療があります。
iPS細胞を用いた治療については京都大学などですでに治験が始まっています。
今回、アメリカカルフォニア大学サンディエゴ校のXiang-Dong Fu氏らはマウスの実験ではありますが、「PTB」というRNA結合タンパク質に注目した報告を2020年6月Natureに報告しました。
PTBは細胞内の遺伝子のスイッチのオンとオフに関係するタンパク質で、PTBの働きを抑える実験にて、脳内に存在する支持細胞という細胞が、ドパミンを作る細胞に変わったことを発見し、パーキンソン病でみられるような運動障害が改善したと報告しています。
この、特定の種類の細胞が別の細胞に変わることを分化転換と呼びますが、障害のある細胞を他の細胞に変えることにより機能が回復するというこの技術が確率されればパーキンソン病だけではなく、脊髄損傷など他の病気の治療にも役立つことが期待されます。
現在はマウス実験レベルで、これからの人の治療に用いることが出来るかは、多くの研究と安全性の確認が必要となりますが、根本的な治療法の可能性が少しでも広がることを期待します。
おばた内科クリニックは、パーキンソン病や認知症などの脳神経疾患を専門に力を入れて診療行っています。
糖尿病や高血圧、高脂血症などの生活習慣病含めこれからも定期的に情報発信させて頂きますので、今後ともよろしくお願いいたします。
原著論文
Reversing a model of Parkinson’s disease with in situ converted nigral neurons
Nature volume 582, pages550–556(2020)